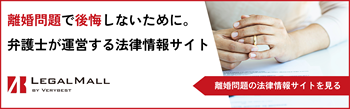【メール相談】せめて今直ぐ別居したいです!
相談内容
結婚12年目、小学5年生の娘と、3年生の息子がおります。数年前より私に離婚願望あり、もう精神的にも限界で離婚したいです。
せめて今直ぐにでも別居したいと思っています。
離婚理由は将来への不安と、夫の私や子供たちへのモラハラです。
親権は私が取る事について、夫も納得しております。
夫は自営業で、私と二人だけでやっています。
私がミスをすると口汚くののしられ、会話もしたくありません。
家計や、会社を助ける為に私が独身時代に貯めたお金も約200万円ほど出しています。
また、私名義で400万円金融機関に借金があります。
私のお給料も出たりでなかったりです。
別居したいのですが、元手が無く、引っ越し費用等を捻出出来ずやむを得ず同居している、というのが実情です。
このような状態ですが、一刻も早く離れたいです。よろしくお願いいたします。
アドバイス
夫と二人三脚で事業をやっているものの、厳しい経済状態で、ご自身名義での負債も余儀なくされ、その金額も相当額ですね。そのうえご家族へのモラハラですから、離婚を考えられても当然かと思います。ただ、母子家庭に様々な公的支援があるというものの、お分かりのように、手元にまとまったお金がないと、その後の生活が早々に立ち行かなくなるというのもその通りです。
お気持が離婚でしっかり固まっていらっしゃるなら、やはりしっかり準備をする必要があります。
離婚しても、夫の今の状態から、いくら養育費がとれるかわかりません。
新しいお仕事も探さなくてはいけませんし、誰か助けて下さるかたはいらっしゃらないのでしょうか?
一時的でもご実家で暮らすことは可能でしょうか
何にしても、シングルマザーとして生きていくには、公的支援だけでなく、親族やお友達など、サポートしてくださる方がいないと厳しいですね。
公的支援は各自治体によって違いますので、今後暮らしていきたい自治体でよくお話をお聞きになることです。
また、貴女様名義の借金のことなどは、無料相談をされている弁護士さんや、法テラス(正式名称・日本司法支援センターは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です)自治体の無料法律相談などでご相談されてはいかがでしょうか。
併せて、離婚に際しての費用のこともお聞きになるとよいと思います。
夫に対して、お気持ちも残っていないのであれば、色々な意味でこれ以上傷が深くならないうちに、行動された方がよいと思います。
離婚・夫婦修復のお悩み ひとりで悩まずお気軽にご相談ください
※海外からおかけになる場合はこちらから
電話:03-6274-8061
メール:caratokano@gmail.com
※土日祝は電話のみの受付となっております。WEBからお申し込みの場合、翌営業日のご返信になりますのでご了承ください。
お急ぎの場合はフリーダイヤル(0120-25-4122)にてお申し込みください。
電話:03-6274-8061
メール:caratokano@gmail.com
※土日祝は電話のみの受付となっております。WEBからお申し込みの場合、翌営業日のご返信になりますのでご了承ください。
お急ぎの場合はフリーダイヤル(0120-25-4122)にてお申し込みください。
決済方法
- 料金お振込み先
-
三菱UFJ銀行 渋谷中央支店
普通預金 0757866
株式会社ウェルマッチ - カード決済
-
カード決済ページはコチラ